こんにちは。
スポーツメンタルコーチの加藤優輝です。
よくアスリートから、「休み方が分かりません」、「休みの日も練習してしまいます」、「遊ぶくらいなら練習した方がいいと思っています」このような相談がきます。
真面目で努力家でストイックなアスリートだからこそ、起こりうる悩みでもあるなと感じます。
そんなアスリートにこそ大切にして頂きたいことがあります。
それが、「競技中に使っている脳を休ませる」ということです。
そしてそのような休みの過ごし方が、結果的にパフォーマンスを向上するきっかけとなります。
今回は、「競技中に使っている脳を休ませる」とはどういうことなのか。
そして、どんな休みの過ごし方がパフォーマンスの向上のきっかけになるのか。
2分〜3分ほどで読めますので、ぜひ最後までご覧ください。
目次
① “私も現役時代は休まずに練習するような選手でした”
② “普段使っている脳を休ませることが大切な理由”
③ “競技中に使っている脳を休ませるとパフォーマンスが向上する”
④ “そもそもどうして休むことができなかったのか?”
“私も現役時代は休まずに練習するような選手でした”

皆さんは、休みの日でも練習をしてしまったり、競技のことを考えてしまったり、遊ぶことが無駄だと思ってしまうような経験はないでしょうか?
ちなみに私は現役選手時代、まさに休むことができない人間でした。
当時は休むことに対してこんな思い込みを抱いていました。
・他の選手との差が生まれる
・他の選手は努力しているかもしれないからやらなきゃ
・疲れていても努力し続けることが大切
・誰よりも練習すれば夢や目標は実現できる
そんなことばかりを考えながら競技をしていました。
結果、どんな競技人生となったかというと、
・疲労が抜けず試合ではいいパフォーマンスを発揮することができない
・膝がボロボロになってボールが蹴れなくなる
・練習量に対して結果がついてこなく自信を失う
などといった、目標を実現するためにやっていたはずの努力が、目標を遠いざけるための努力になってしまいました。
そして、日を重ねるにつれて、目標を実現するのが無理かもしれないと思うようになり、不安な感情を抱くように。
結果的に、日々の練習が不安な感情を誤魔化すための練習に変わり、燃え尽き症候群によって現役引退。
あの当時、「休む目的が明確になっていて、休んでいる間にも成長はしている、練習することだけが努力ではい」と気づくことができていたら、また違った競技人生になっていたと思います。
その後、当時の自分がどうして休むことができなかったのかを知るために脳科学や心理学・スポーツ科学などを学んでいると、ある衝撃的なことに気がつきました。
それが競技中に使っている脳を休ませることがパフォーマンスの向上に繋がるということです。
なぜ脳を休ませることでパフォーマンスの向上に繋がるのか。
それについてこれからお伝えしたいと思います。
“競技中に使っている脳を休ませることが大切な理由”
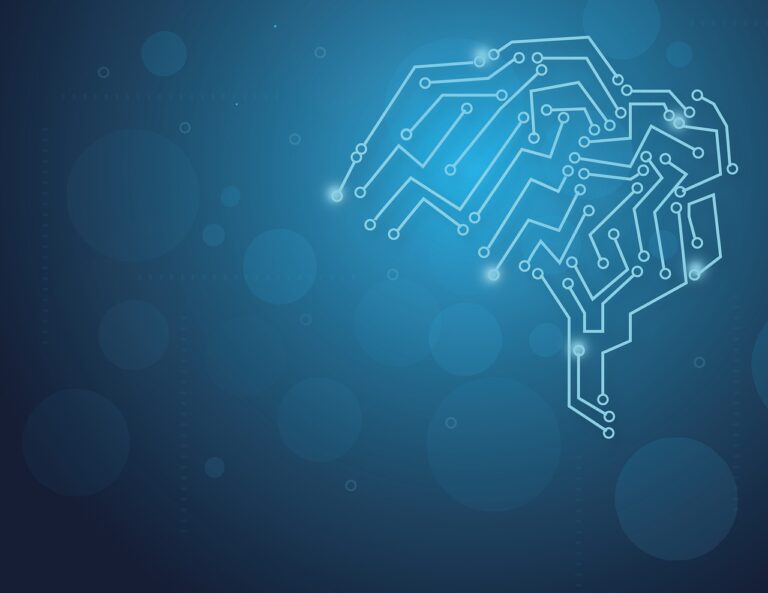
私がサポートしているアスリートには、オフの日は競技のことは一切考えずに、競技とは関係ないことに没頭して自分の時間を楽しんで欲しいと伝えています。
なぜなら、競技で使う脳の部分をしっかり休ませて、オフ明けにリフレッシュした状態でいてほしいからです。
脳には、運動や思考、感情など、人間の様々な活動をつかさどる特定の部分が存在し、それぞれ密接にネットワークを作りながら活動しています。
運動しているときは、運動制御や空間認知に関する部位が活性化し、勉強しているときは、記憶力や創造力、情報処理に関係する部位が活性化しています。
そしてある研究によると、脳のある特定の部分を休ませるためには、それとは全く異なる活動をして脳の別の部位を活性化させることが必要であるということが明らかになっています。
例えば、練習中や試合中などの競技生活で普段から使っている脳を休ませるためには、それとは全く異なる活動をして脳の別の部位を活発化する必要があります。
そうすることで、はじめて競技生活で使っている脳の休息が得られるのです。
つまり、脳の休息のためには、ただ身体を休ませるのではなく、積極的に活動し、脳を別のことへ使う必要があるのです。
サッカーやバスケなどの球技スポーツはでは、常にボールや相手を認識し、見て、判断して、実行するという脳の活動が行われています。
この活動を繰り返し行うと何が起こると思いますか?
走り続ければ疲労していくように、脳も使い続ければ疲労していくのです。
スポーツで使っている脳の特定部分を休息させなければ、身体を休ませたとしても、「疲れた」と感じてしまいます。
つまり身体だけを休ませるのではなく、同時に脳も休ませることが大切なのです。
だからこそ、競技とは異なる活動をすること、すなわち、勉強したり、全く異なるスポーツをしたり、娯楽や趣味に没頭することで、競技で使う脳を休ませることができます。
“競技中に使っている脳を休ませることでパフォーマンス向上に繋がる”

これらのことから、競技中に使っている脳を休ませることが大切であることはご理解頂けたかと思います。
一方で、「競技中に使っている脳を休ませるなら、何もせずぼーっと過ごすだけでいいのでは?」こんなことを思う方も少なくないかもしれません。
ですが、何もせずぼーっと過ごすだけの時間を増やすだけでは、脳は休まらないと言われています。
実は人間の脳は、何もしないでいるときにもDMN(デフォルト・モード・ネットワーク)という脳の回路が過剰に活動し、脳のエネルギーの60%〜80%を無駄遣いしているケースがあります。
つまり、脳内に老廃物が溜まり続けている状態であるとも言えます。
だからこそ、オフの日はただぼーっと休むだけではなく、競技中に使っていない脳を積極的に使っていきたいです。
またそうすることによって、競技中に使っている脳を休息させ、回復を促し、パフォーマンスの向上にも繋がっていくとある研究でも言われています。1)
“そもそもどうして休むことができなかったのか?”

そもそもどうして休むことができなかったのでしょうか?
この根本的な部分が改善されないと、本当の意味で改善されたとは言えません。
なぜなら、その根本的な部分が原因で休めないという結果が生まれているからです。
その根本的な部分とは、言わば無意識の習慣、思い込みとも言えます。
もしかすると、過去に「誰よりも練習したら結果が出た」という経験をしたからかもしれません。
過去に所属していたチームで、「遊ぶ暇があるなら練習しなさい」と指導されていたかもしれません。
尊敬する人から、「誰よりも努力することで夢や目標を実現できる」と聞かされた過去があるからかもしれません。
果たして本当にそうだと言い切れるのでしょうか?
それは思い込んでいるだけなのではないでしょうか?
どんな人も、過去に経験したことをもとに、思い込みというセルフイメージを作り上げています。
その思い込みが原因で活躍できないアスリートをたくさんいます。
しかし、自分の力でその思い込みに気づくのは簡単ではありません。
なぜなら、自分自身はそれが正しいと思い込んで日々競技と向き合っているからです。
つまり、その思い込みは無意識の習慣となっているのです。
だからこそ、その思い込みに気づいてもらうために、スポーツメンタルコーチが存在しています。
うまくいかないときは、うまくいかない理由があります。
うまくいく人には「うまくいく習慣」があり、うまくいかない人には「うまくいかない習慣」があるのです。
今回は普段使っている脳を休ませることで、パフォーマンス向上に繋がるという点についてをお伝えしました。
しかし、向上させたパフォーマンスをここ一番で発揮するには、他の条件を満たすことも必要になります。
では、その条件とは何なのか。
その条件について誰もが学べるように、完全無料のメールセミナーという形でご用意しました。
これを読めば、誰もがハイパフォーマンスを発揮できるような仕組みになっています。
・ここ一番で結果を出したい!
・最高のプレーで活躍したい!
・自分の全てを出し切りたい!
・結果を残して夢を叶えたい!
そんな方は下記のボタンからご確認ください。

このコラムの著者






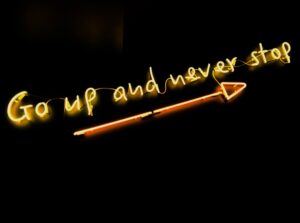




コメント